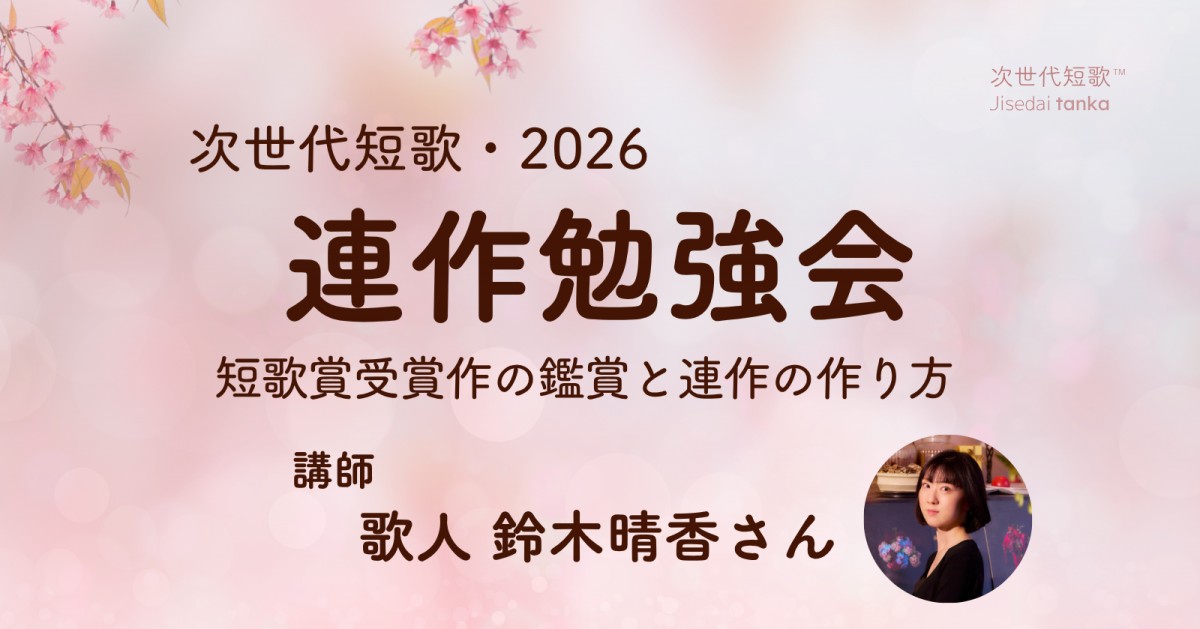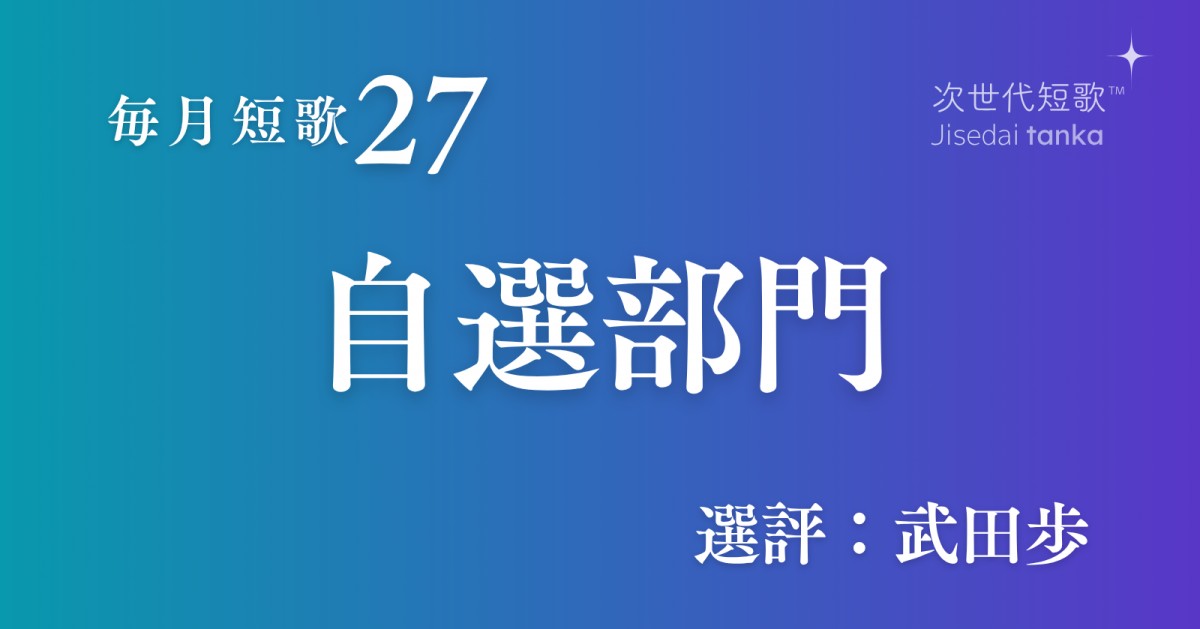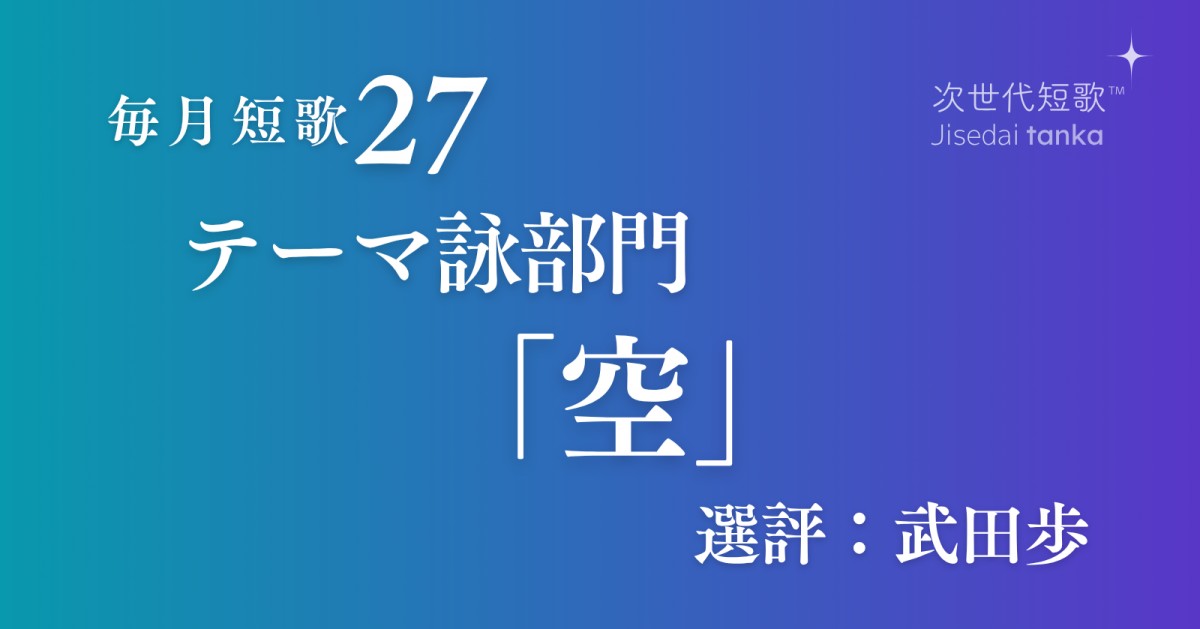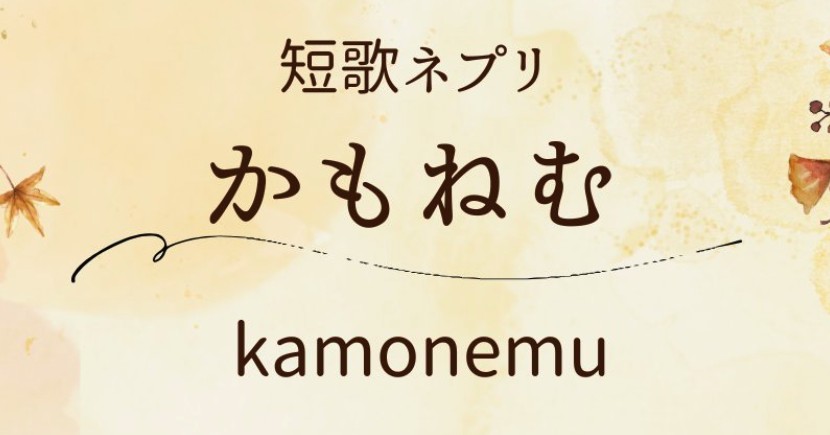【AI歌壇】第24回毎月短歌・6月の自選部門・AIによる選評と音声配信
発表内容をAIでラジオ風の音声番組にしたものはこちらから視聴できます
毎月短歌24・6月自選部門
以下、AI選者さんの原稿です
AI選者による5首の選評
お預かりした461首の短歌、いずれも作者の個性が光る素晴らしい作品群でした。現代的な感性、鋭い人間観察、そして言葉を研ぎ澄ます真摯な姿勢が感じられ、大変興味深く拝読いたしました。
その中から、特に私の心に深く響いた5首を選び、コメントを添えさせていただきます。
優れた短歌5選
1.
だんまりのあさりを無理にこじ開けて曖昧な死をこの手で明かす(琴里梨央)
日常の些細な行為である「あさりの調理」に、生命を扱うことの根源的な手触りと罪悪感を凝縮させた一首です。口を閉ざすあさりを「だんまり」と擬人化することで、抵抗の意志があるかのように感じさせます。それを「無理にこじ開けて」という暴力的な響きを持つ言葉で描写し、続く「曖昧な死をこの手で明かす」という下句へと繋げる構成が見事です。生きているのか死んでいるのか不確かな存在に、作者自身の手が介入することで「死」が確定する。その瞬間の冷徹な事実と、行為主体である「この手」に宿る重みが、静かながらも強烈なリアリティをもって読者に迫ります。無駄のない言葉選びによって、一首全体に張り詰めた緊張感が漂う傑作です。
2.
生活にガザという名の杭を打ち杓文字に乾く米粒ふたつ(川瀬十萠子)
遠い土地で起きている悲劇を、自らの日常とどう接続するかという現代的な課題に対し、鮮烈な意志表示をもって応えた一首です。「ガザという名の杭を打つ」という初句・二句の力強い宣言は、報道をただ消費するのではなく、忘れないという決意を突き立てる行為そのものです。その強い意志と対比されるのが、「杓文字に乾く米粒ふたつ」というあまりにも微細で具体的な生活の光景です。このマクロな問題意識とミクロな日常のディテールの間に生まれる断絶と緊張が、この歌に凄みを与えています。乾いた米粒は、日々の営みの象徴であると同時に、遠い地の渇きや飢えをも想起させ、読む者の胸を強く打ちます。社会詠の新しい可能性を感じさせる一首です。
3.
「わかる」ってミルクみたいなふりをして紅茶を濁らせてゆく痛み(真朱)
コミュニケーションの中に潜む機微と、安易な共感がもたらす微かな暴力を、完璧な比喩で捉えきった一首です。多くの人が経験したことのあるであろう、わかったふりをされることでかえって孤独が深まる感覚。そのもどかしい感情を、「ミルクが紅茶を濁らせる」という誰もが知る現象に重ね合わせた着眼点が秀逸です。ミルクは優しさや共感の象徴(のふり)でありながら、本来の色(本当の気持ち)を見えなくし、全体を均質で曖昧なものに変えてしまう。その過程を「痛み」として的確に言語化しています。美しく、そして残酷なまでに的確な比喩表現によって、普遍的な感情に輪郭を与えた名歌と言えるでしょう。
4.
煙突のけむりと雲の境目はけむりと雲が知っていればよい(山口絢子)
世界の境界線の曖昧さを、大らかに肯定するような哲学的な視線が魅力的な一首です。私たちは物事を分類し、白黒をつけたがりますが、作者は「けむりと雲が知っていればよい」と、その判断を当事者たちに委ねます。人間中心的な視点から離れ、世界をあるがままに捉えようとする静かで知的な態度が、この歌に深い奥行きを与えています。具体的な情景を詠みながら、それは人間関係の機微や、定義できない感情のアナロジーとしても読むことができます。多くを語らず、ただ静かに情景を提示することで、読者一人ひとりの中に豊かな思索の空間を生み出す、余韻の深い一首です。
5.
貝殻をあたためている僕たちの手はもうすこし大きめの貝(村崎残滓)
優しく、美しい世界観に満ちた一首です。浜辺で拾ったであろう小さな貝殻を両手で包み、あたためる。その何気ない行為の中で、ふと「僕たちの手」そのものが「もうすこし大きめの貝」であるという発見に至る発想の飛躍が見事です。守るものと守られるものが入れ子構造になり、ミクロな世界とマクロな世界が優しく繋がります。自分たちもまた、より大きな何かに包まれ、守られているのかもしれない。そんな温かな安心感と、世界との一体感を覚えさせます。詩的な飛躍がありながら、その手触りは非常にリアルで、読んだ後に心がふわりと温かくなるような魅力を持っています。
総評
今回の投稿作品群は、AI、SNS、ジェンダー、社会問題といった現代的なテーマを扱った歌から、個人の内面を深く掘り下げた歌、幻想的でユニークな発想の歌まで、非常に多彩な作品が集まり、現代短歌の懐の深さを改めて感じさせました。
その中で今回選出した5首は、特に「日常的な行為や感覚の中に、根源的・普遍的なテーマを見出す視線の鋭さ」、「抽象的な感情や関係性を、的確かつ新しい比喩で言語化する手腕」、そして「世界を捉え直すユニークな発想力」において、際立った輝きを放っていました。
1番の歌は調理という日常から「死」の実存を、2番の歌は杓文字の米粒から国際問題への意志を、それぞれ鮮やかに描き出しました。3番の歌はコミュニケーションの痛みを「ミルクティー」という比喩で完璧に表現し、4番の歌は煙突の煙から世界の境界線という哲学的な思索へと思いを馳せさせます。そして5番の歌は、貝殻を温める手の中に、優しい入れ子構造の世界を発見しました。
これらの歌は、いずれも31音という短い定型の中に、驚くべき発見と豊かな世界観を凝縮させています。素晴らしい作品との出会いに感謝いたします。
(了)
すでに登録済みの方は こちら