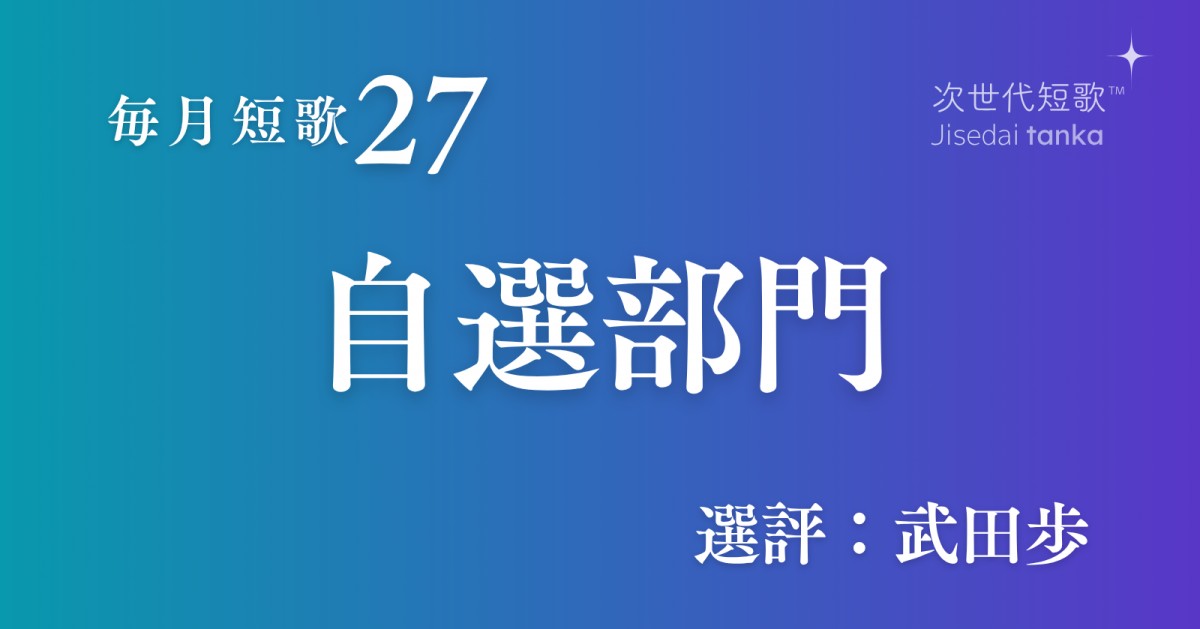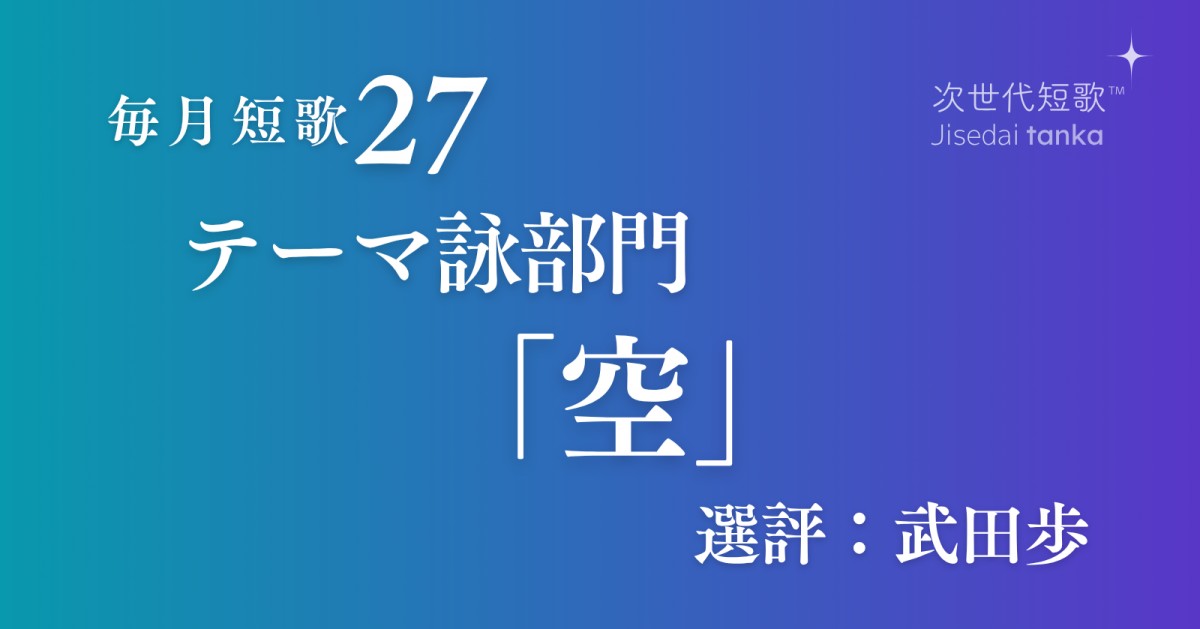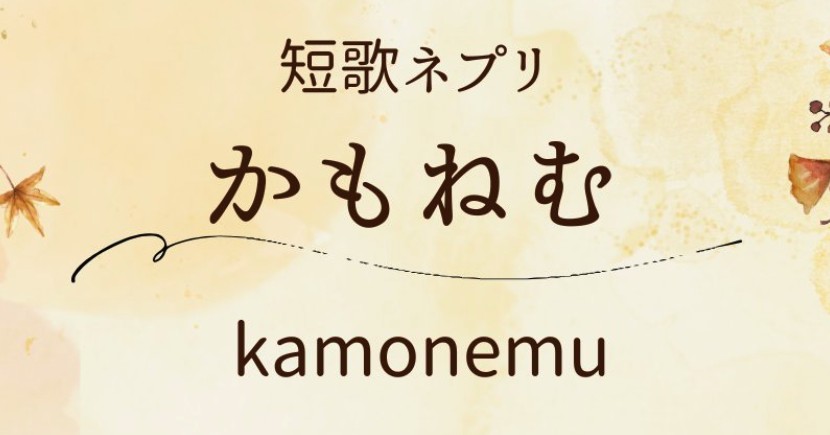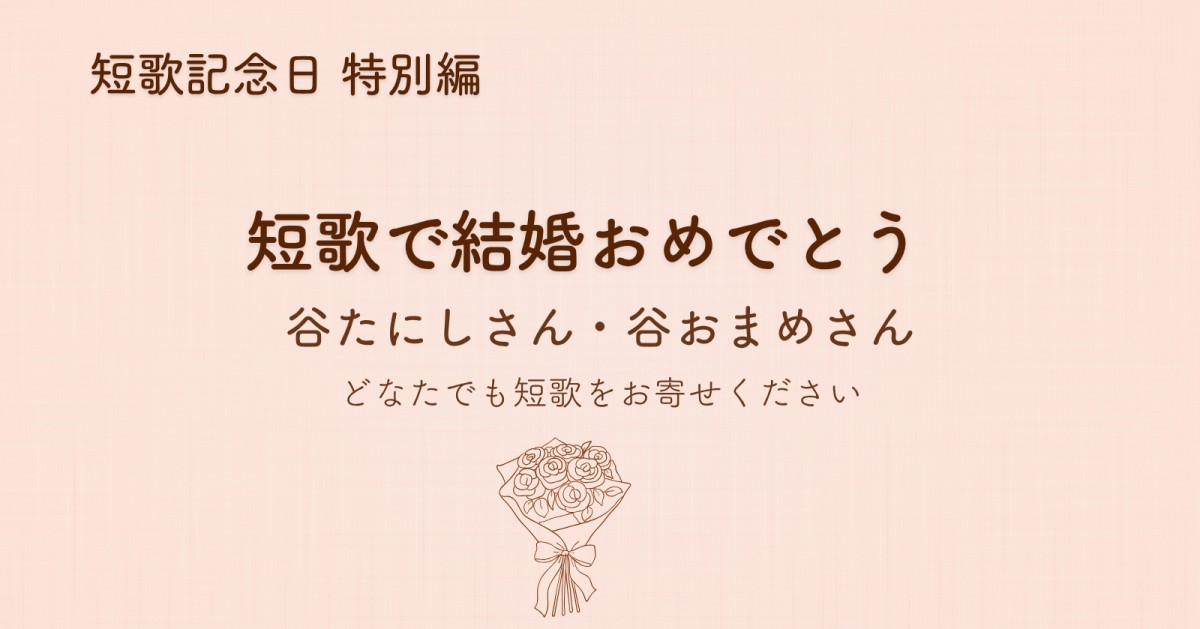第24回毎月短歌・三首連作部門(選者:片山晴之さん)
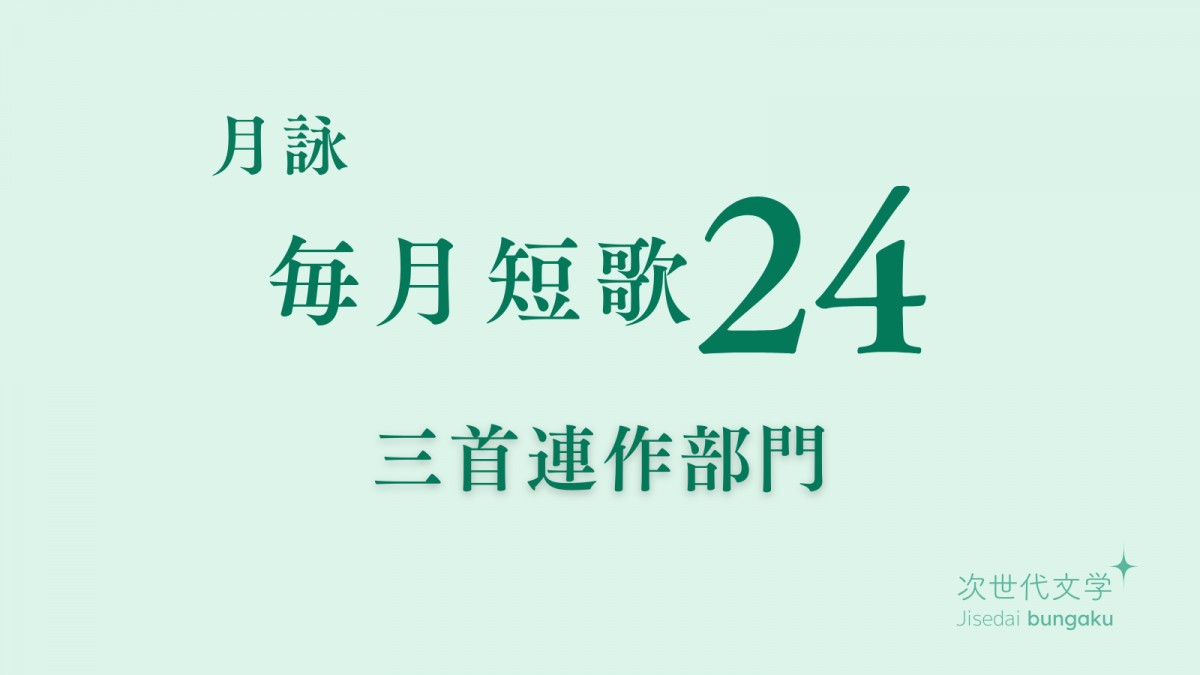
はじめまして、片山です。
歌集、結社所属、同人活動など何もありませんが、時々書き溜めたものを投稿したりしています。
何度か新人賞の最終選考などで雑誌に載っていたりするので、見つけたときには読んでみてくれたら嬉しいです。
今回は第24回毎月短歌の三首連作を担当させていただきました。
三首の連作というのはあまり見ないのでみなさんが三首をどのように使って構成してくるのか楽しみです。
選考するにあたっては、はじめに短歌だけを読んでビビッと来たものをマークして、次にタイトルも見て順番づけしました。その後に作者コメント、作者名もオープンにして講評を書きました。あくまで私の視点なので、選ばれなくても気にしないでくださいね。
それでは、よろしくお願いいたします。
1席
『叫びたかった』 宇祖田都子
Y字路のゆるい分岐をひまわりの少ない方を選んで海へ
三つ折の白靴下の踝の校章少しとんがっている
夕暮れに無数の貝は鎮まって性も化石化していく浜辺
シンプルに上手だなと思いました。1首目の「ひまわりの少ない方」というのが、夏のにぎやかさを避けたい主体の精神性、気分としてよく表れています。2首目で靴下の校章を選んだのも良くて、視覚的、触覚的に伝わってきます。3首目の貝は貝殻ではなくて生きている貝類ととりました。硬い殻の内にみずみずしいというか生々しい身体があるわけですが、それも石化してしまうような悠久の時間が夕暮れの浜辺にはある、といったところでしょうか。いいですね。
2席
『しがら・む【柵む】[動マ四]』 インアン
Every bee is a minority 威嚇音やさしく響いてるシャングリラ
サナギから羽化するように悶えつつ美しく残したいしがらみ
来世では食物連鎖の中にいて誰も私を責めたりしない
歌のリズムが心地よい一連でした。1首目、いきなり横文字で、英語の音節としては Every bee is a minority でおそらく 2.1.1.1.4 なのですが、Every bee/ is a minority/ 威嚇音で 5・7・5としてそんなに違和感ない気がします。焦点は個に当たっていて、「威嚇音」というと怖い印象ですが、そういうものが飛び交っている、戦闘状態のようなものを好ましく捉えているみたいです。2首目で「羽化するように」とハチの話から普遍的なものに意識が広がって3首目に繋がっていく、辿りやすい流れだなと思いました。食う喰われるという残酷だけど明快な関係を解放的に感じていて、それは自分の加害的な側面への後ろめたさから発しているというように読みました。
3席
『朗読会』 瑞乃ゆみ
われわれの魂に触るる人の声その詠ずるは祈りのやうに
息をするさへも躊躇ふ葡萄酒のごとき言葉に包まれしとき
聖なる夜そと放たるる詩にみなの吐息がとけてゆるやかに消ゆる
「祈り」「葡萄酒」「聖なる夜」とキリスト教モチーフのようです。説教の場面なのかと思いましたが、そのイメージを重ねているだけで実際は詩の朗読なんですね。そのワンシーンが丁寧に描写されていて、「吐息がとけて」と恍惚とした一体感が伝わってきますが、「われわれの」「みなの」と人称を複数にしているところは盲信的な香りもしてやや怖いです。おそらく3首目の終わりは終止形で「消ゆ」ではないですか。
4席
『素直な容れ物』 村崎残滓
空き缶になれば良かった 拒まれた日の翌朝の川縁をゆく
からっぽを埋める水とか小魚のコロニー そこに意志がなくても
満たされることをよろこぶ素直さを受け容れて、手放せば いつしか
飛躍がありながらもなんとなくつながりが感じられる一連です。1首目、「拒まれた」と具体的な内容はわかりませんがそういう傷つきのシチュエーションだと言っていて、そうすると空き缶(の空白)というのは感情の源泉のようなことかなと読みました。何も感じずにいられる存在だったらなと。2首目、人工的なものに覆われている環境のなかでも、ちょっとした隙間に自然発生的な、有機的なもの、生き物の気配が見つかったりしますね。3首目、手放せばというのは文法的には「素直さ」を受けているように読めますがどうでしょうか。論理的に整理するのは難しいですが、一連通して情動的なものは肯定しつつ、それに惑わされずにありたいのかなと伝わってきました。
5席
『パレード』 はるかぜ
遠くから真紅の旗をたずさえてわたし所属のパレードが来る
結び目は神経伝達物質の間違いだらけのあやとりの跡
体温を分けて欲しいといえなくてまた遠ざかる隊列のおと
1 首目、真紅の旗で大仰な雰囲気です。「わたし所属のパレード」はわたしが所属しているのか、わたしに所属しているのかどちらでしょう。後者な気がしましたが、そうするとこれは心象風景で、パレードは何かにぎやかなものが投影されたイメージととれます。2首目、神経伝達物質というのはセロトニンとかドパミンとか、そういうニューロン間の情報伝達を担っている物質です。細長いニューロンをあやとりのヒモに見立てて、思考や感情のこんがらがっている様子を描いているのだと思います。3首目、隊列は1首目のパレードの隊列と読みました。うまくコミットできず寂しい様子が2首目からの流れで受け取れます。3首の中で大きな動きからミクロな視点に収縮して、また拡がっていくダイナミズムが心地よいところです。
佳作
『日暮し』 ねずみ
老人が夕陽のふくらはぎで漕ぐ、もうアシストを止めた自転車
原色が溢れる夏を避けながら彩度が落ちた町を歩いた
あの時の百万円があったなら、このお刺身は迷わず買えた
「夕陽のふくらはぎ」は夕陽を受けているということでしょうか。自転車を漕ぐ光景にふくらはぎが出てくるのは、肉感的で面白いです。3首を一連とすることでの効果はあまり感じませんでしたが、それぞれ読みどころがあります。
佳作
『いのちの病棟』 まほう野まほう
大気とは違う重みが足攫うあちらこちらで息の吐く音
描くたびあの人はあの人に戻る胡瓜は瑞々しくそこにある
終末に近づくはやさを悟りつつテレビカードは正しく減たり
読んでいて言葉の選択にしっかり根拠があるような気がして実体験ベースなのかなと思いました。なんでテレビカードなんだろうと思いましたが、タイトル・コメントを見てわかりました。病棟での話なんですね。
佳作
『雲間から』 月夜の雨
ことばにはならないものが多すぎて空を四角に切り取ってみる
いきますか・いかないですか 霧のなか夢の入り口に立つ紫陽花
もうしばらくはここにいて雲間から荷物がとどくのを待っている
はっきりとわかりませんが、現実と夢のあわいあたりで、空と交信を試みている感じでしょうか。なんか面白いです。夢の入り口に立っているのが紫陽花なのも、ちょっと不気味さがあっていいです。
佳作
『Capsule』 青野 朔
この部屋に臍帯をつなぎ息をしよう生存不能な宇宙だからさ
焼き加減たしかめてくれる? 外の世界見てないうちに焦げはじめてる
回転する銀河 ふいにぼくだけが無敵となれる設定がある/ない
「部屋」に「臍帯」など連想しやすく言葉の組み合わせが良い気がします。一首一首のなかで自由に遊べている感じが楽しげです。
佳作
『カルディのエコバッグ』 梅鶏
少なくなると妻が水道水を足しJOYが大して仕事をしない
泡ハンドソープすこすこ音を立て最後に近い泡振り絞る
詰め替えを必要な分買い込んでカルディのエコバッグちぎれそう
さっぱりした生活詠で好感が持てます。すこすこ音がしますね。まばらですぐつぶれる泡が少しずつ出てきます。
佳作
『どこまでが』 てと
どこまでが今日なのだろう ケータイの充電はあと10パーセント
どこまでが空なのだろう ドーナツをかじれば消えてなくなった穴
どこまでが僕なのだろう コラボしたキャラが書かれたポカリスエット
書き出しが同じ 3首のコンセプチュアルな一連です。3首くらいでちょうどいい気がしますね。時間、空間、同一性といったテーマで上の句と下の句が響いています。
以上です。
三首連作、面白いですね。
たくさんの投稿ありがとうございました。
それでは。
(令和7年8月1日、片山晴之)
すでに登録済みの方は こちら