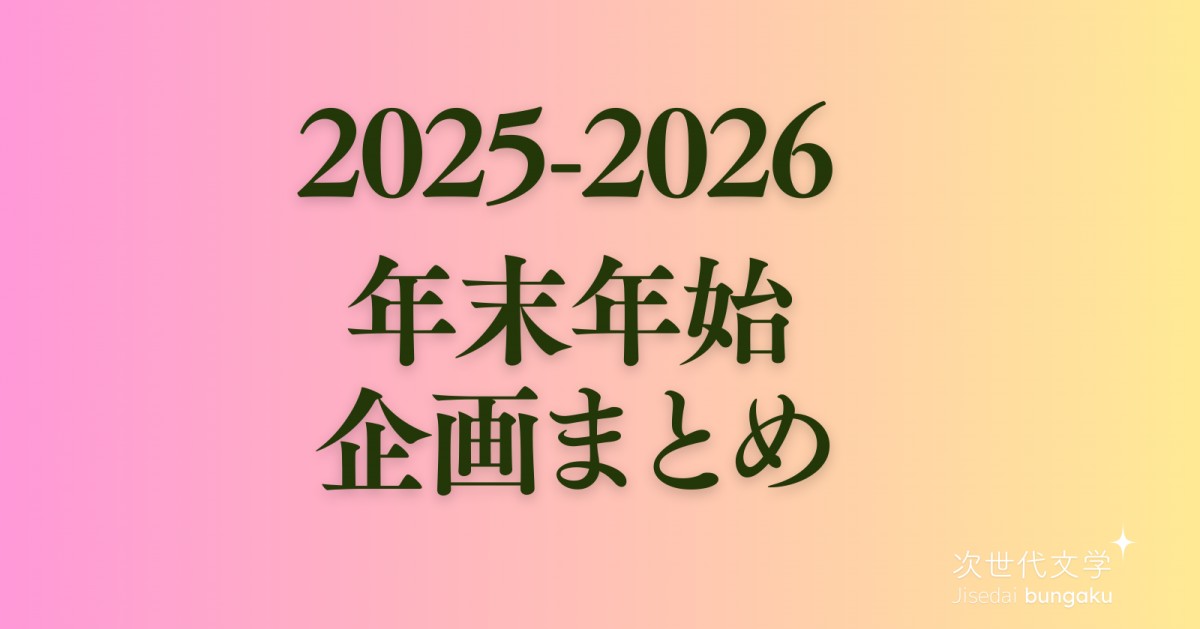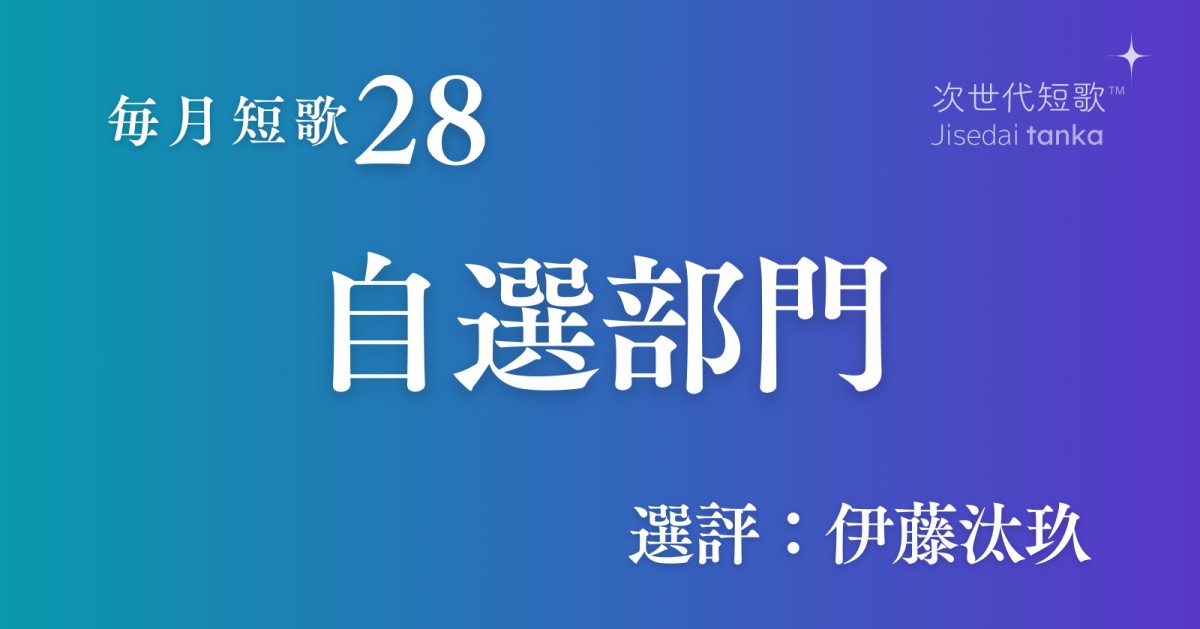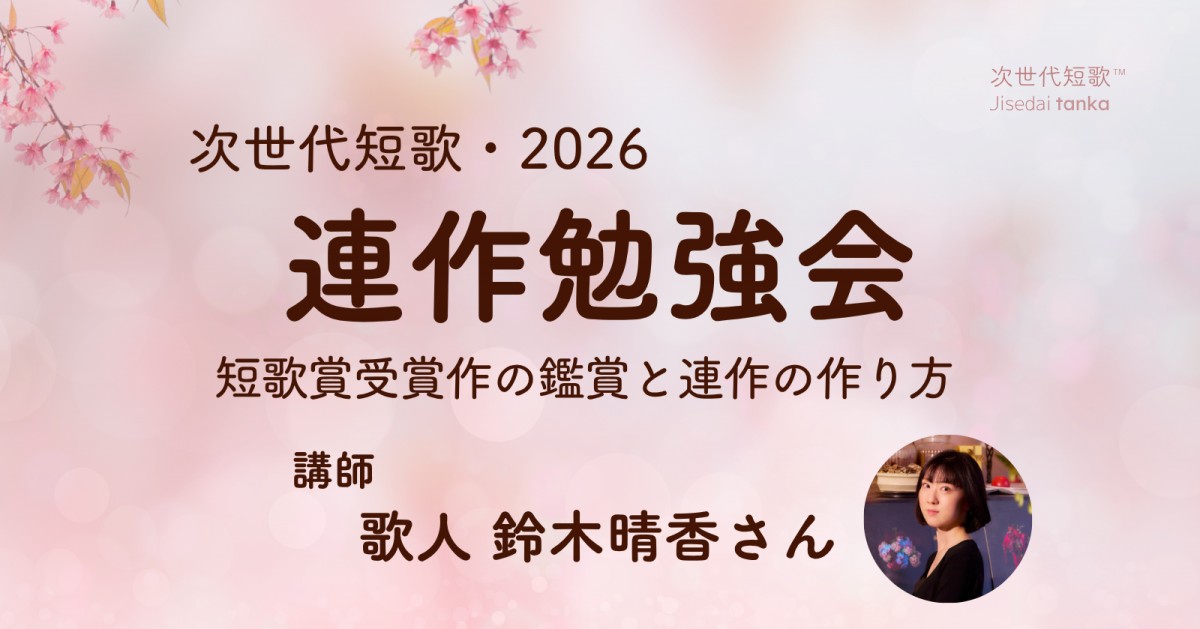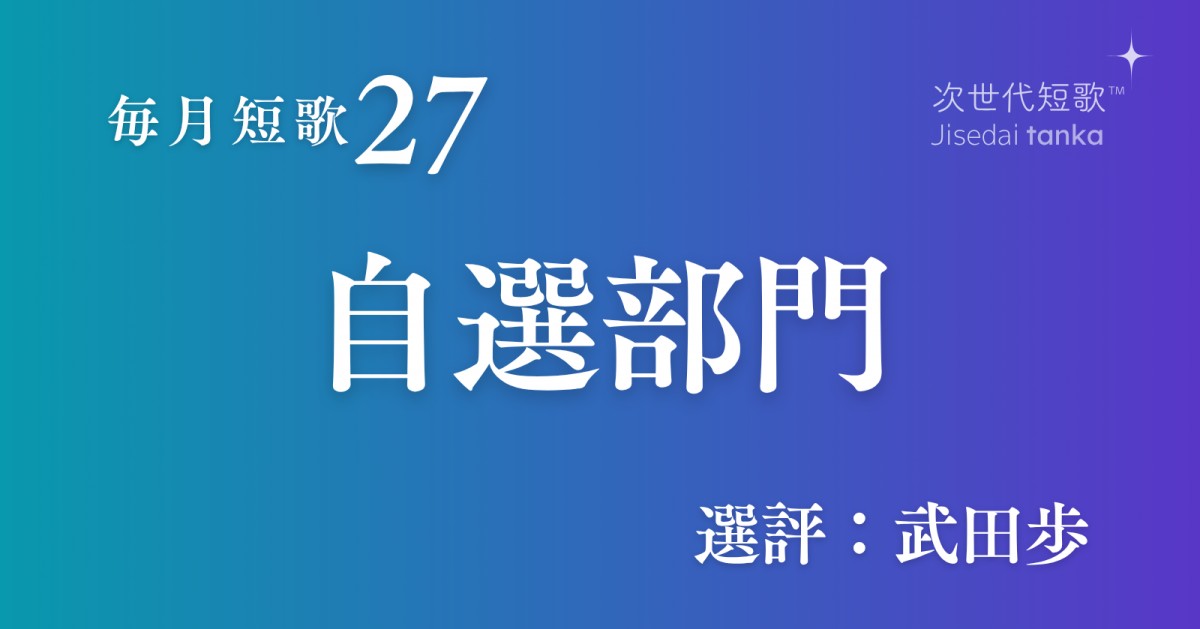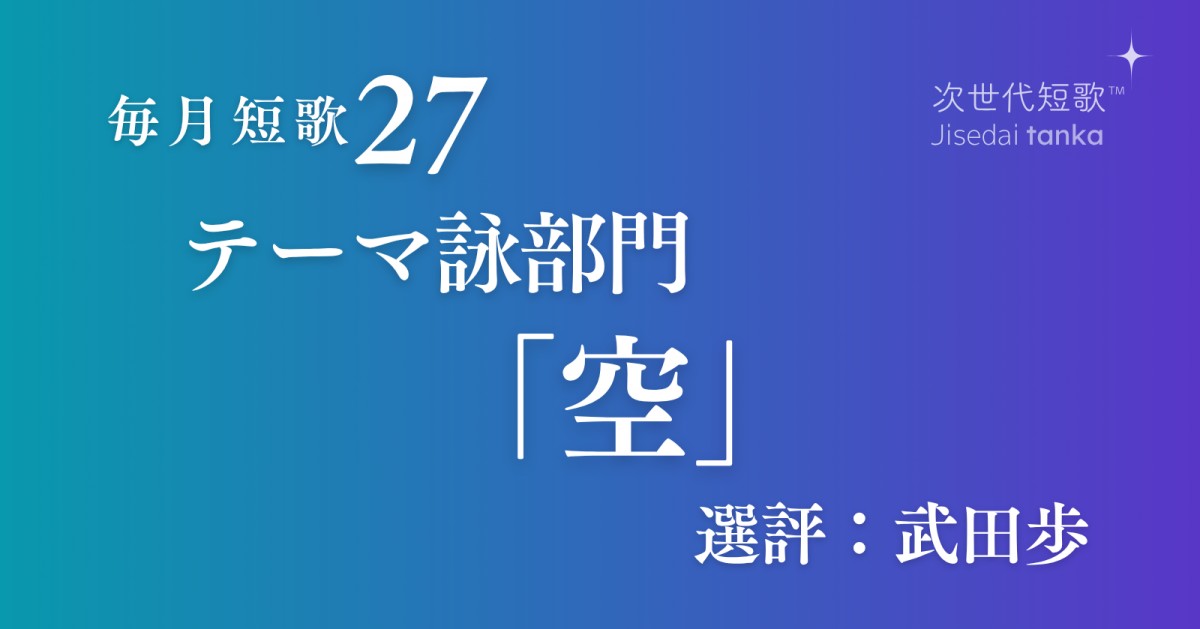【短歌日記】toron*「ナイフのように爪先立ちで」(第20回)10月12日〜10月18日
[次世代短歌プレミアム]

[短歌日記]
ナイフのように爪先立ちで 第20回
toron* 日記 10月12日〜10月18日
されど銀河帰郷して墓寄り添ひぬ父の墓標は書物のなかに
10/12(土)
きょうから6泊7日で青森へ。朝9時過ぎにJR奈良駅から高速バスでダイレクトに伊丹空港へ。そこから13時に飛び立って15時過ぎに青森県・三沢空港に着く。
……と書くと、けっこうあっさり青森に入れたな、という感じがしないでもないのだけれど、実際、飛行機に乗った最後が6年前の仙台行き以来だったので、搭乗システムの電子化とか手荷物検査のなんだかんだは緊張の連続だった。とはいえ、奈良駅からバス1本で空港まで来れたのはかなり楽だった。
JALでは1日に4本三沢空港への便が出ている。三沢は寺山修司が幼少期……空襲で疎開してきてからの約4年間を過ごした町である。米軍基地が敗戦当時から未だにあって、寺山修司の母親も、夫を亡くしてからそこに働きに出ていたらしい。
寺山修司記念館もこの空港から車で15分くらいの距離なのだけど、きょうはスルー。きょうは明日の目的地ためのほぼ移動日なのである。レンタカーを借りて、むつ市を目指す。
むつ市は青森県の北端、下北半島。斧のようなかたちをした部分である。
「最も子殺しの多い青森県。下北半島は子に向けてふりかぶるその斧のかたち……」
と、いう文章を自分も確か寺山修司の文章で見たことがある。
自分はゴールドペーパードライバーなので、運転はオール夏生さん。奈良もまあまあ広いのだけど、青森はさらに広い。
信号がまず少ないし、ピクミンブルームの花もキノコもほとんど表示されない。キノコがたまに生えていても誰も入っていないパターンがほとんどで、青森県でピクミンするのはたいへんだろうな……ということも、思ったりする。そして、ちょっと山道を通ると電波があっさりなくなる。
六ケ所村あたりから遠景・近景に風力発電機が混ざりだす。夕暮れのなか逆光で見ると、エヴァの使徒っぽさもある。
ガソリンも安い、野菜も安い。朽ちていくしかなさそうな家屋を何軒も通り過ぎる。
18時にはむつ市に入る。暗い、けれども奈良とは別の夜の暗さだ。
行きのバスから太宰治の『津軽』を読み始めていたのだけど、ちょうど自分たちと似たようなルートを辿っていた。
「風景というものは、永い年月、いろんな人から眺められ形容せられ、謂わば、人間の眼で舐められて軟化し、人間に飼われてなついてしまって、高さ三十五丈の華厳の滝にでも、やっぱり檻の中の猛獣のような、人くさい匂いが幽かに感ぜられる」
と、太宰も書いていて、この文章の後、本州最北端の風景がどれほど凄愴としているかの形容がつづく……実際そういう暗さで、奈良の暗さはまだまだ「檻の中の猛獣」なのだろう。
それでも、町中にビジネスホテルはいくつかあって、きょう泊まるところは駐車場にもかなり車が止まっていた。自分たちと目的地が一緒のひとも多いのかもしれない。ジャズの演奏会をやって、地域の年配の方が見に来ていたりもしていた。
飲み屋が連なる通りもあって、そこもほぼ満席だった。味噌貝焼き、氷下魚、さんま刺身など頼んで、寒立馬、安東水軍という日本酒を1合ずつ頼む。
事前にガイドブックで見ていたけれど、海産物が美味しいうえにリーズナブルだった。貝焼きについても『津軽』に「私たちは皆、このカヤキを食べて育ったのである」と書いてあり、これがその……! と大事に食べた。
あしたもなかなかの移動になるので、夏生さんは土曜プレミアムの『踊る大捜査線』が終わってシュッと寝てしまった。
わたしの方は『津軽』をもう少し読みすすめてからねむる。
10/13(日)
むつ市の朝は思っていたよりも寒くなかった。きょうは一路、恐山へ。
この旅のメイン……というとちょっと違うのだけれど、恐山秋詣りの日に合わせているので、恐山に合わせてこの旅の他の予定を調整していたりはする。
恐山では「イタコの口寄せ」が有名ではあるが、現在イタコは年2回のお祭りのときしか来ていないらしく、せっかくなのでこの旅程もそのお祭りの日に合わせるか……となった。
イタコに降ろしてほしい誰かがいるという訳ではなく、寺山修司の映画『田園に死す』のイメージを直に見てみたかったのだ。
入山すると、こんな立地なのになかなかの人の多さだった。やはり秋詣り、そしてイタコ目当てのひとも多いのかもしれない。
恐山の社務所のようなところでさっそく「イタコの口寄せ」の看板が出ていて中にはもう15人ほどひとが並んでいた。イタコと依頼者の席の前にはうすい紗がかけられている。
ぼんやり聞こえてくるのは、数珠を揉む音。それにお経と歌の中間のようなものを唱える声……それがあるときピタッと止んで、小声で依頼者に語りかけている感じが伝わってくる。
ひとり降ろしてもらうのに4千円で、1回につきふたりまで降ろしてもらえるらしい。
今の依頼者はどうもふたり降ろしてもらっているようだった。言葉を聞きたいひとがふたりもいる、ということだ。
イタコは眺めるだけで満足なのだけど、もし降ろしてもらうなら誰がいい、という話を夏生さんとくる前にしていた。
夏生さんは「誰も降ろしてほしくない」という返事で、まあ解らないでもない。
わたしも自分のおばあちゃんか誰かを降ろしてもらうのはなんだか違うような気がしている。誰か、といったらやはり思いつくのは寺山修司だけれど、ここのイタコはきっと何度も「寺山修司を降ろしてほしい」と頼まれているようにも思う。
イタコをしばらく眺めたあと、極楽浜の方まで歩く。
あたり一面の岩場で、しかも隙間からところどころ硫黄が噴出していてまさしく「地獄」の果てに、とてつもなく澄んだ湖と白い砂浜があるのである。……たぶん歩いているあいだ、多くの人がそれを「骨のような白さ」だと思うのだろう。
硫黄のせいなのか、水はグリーンに近い澄んだ色で、生きものが全くいないうつくしさだった。
すごいな……学生時代から来たいと思っていたのだけれど、ほんとうに来てしまったのだなあ、と思う。
恐山では噴出する硫黄のためか、献花や線香の代わりにセルロイドの風車が売られていて、参拝者は境内の好きな岩場に差すことができる。
浜辺に近いところに差すと、風の強さでカラカラカラ……とすぐに風景に溶け込んでまわりはじめた。
かくれんぼの鬼とかれざるまま老いて誰をさがしにくる村祭/寺山修司
10/14(月)
きのうは恐山のあと脇野沢港まで移動し、そこからむつ湾フェリーでレンタカーごと蟹田まで。そこからさらに本州最北端・竜飛崎の宿に泊まっていました。なので、きのうもほぼほぼ移動日といっても遜色はなかったかもしれない。
ちなみに恐山の山中、電波はほぼゼロだったのだけど、一瞬だけ電波が入ったので、ピクミンブルームを立ち上げて恐山のキノコに会社のみんなを招集することができた。美潮さんとの約束も、ちゃんと果たせたぞ。
竜飛崎に到着するまでの道は、むつ市の闇より数段濃くて、闇の中に突っ込んで行く感じだった。夏生さんが折々に「わァ…ァ…」「ワ…」とちいかわ的な叫び声をあげていたのでわたしも助手席でまあまあ緊張していたのだけれど、チェックインの時間にもちゃんと間に合った。
温泉から見る海は真っ暗で、ほのかに北海道の方に明かりが見えた。
さて、一夜明けてきょうはそんな竜飛崎の周辺を巡る。あの「津軽海峡冬景色」の碑もあった。碑のなかにスピーカーが内蔵されているようで、ボタンを押すと大音量で津軽海峡冬景色が流れて、なんだかちょっと恥ずかしくなる……恥ずかしくなる必要はないのだが。
竜飛崎には太宰治の文学碑もあった。太宰が『津軽』ではじめて竜飛岬を訪れたときの一節がそのまま彫られていて、
「ここは、本州の袋小路だ。読者も銘肌せよ。諸君が北に向って歩いている時、その路をどこまでも、さかのぼり、さかのぼり行けば、必ずこの外ヶ浜街道に到り、路がいよいよ狭くなり、さらにさかのぼれば、すぽりとこの鶏小舎に似た不思議な世界に落ち込み、そこに於いて諸君の路は全く尽きるのである。」
とのことなのだけど、「鶏小舎似た不思議な世界」って、あまり誉めていないような気がするのだが、この部分を碑にしてしまって良かったのだろうか……。
お昼は青函トンネル記念館併設の道の駅(!)でホタテ丼を食べる。ちなみにセット価格で800円だった。安い……。
連日、なかなかの移動をしているが、きょうも竜飛岬から弘前へ。太宰治記念館に行って生家を見学してから、本日の宿に向かう。
実はきょうの宿はホテル内に天文台が併設されているところだったので、めちゃめちゃ楽しみにしていたのである。ただ、あいにく天気としてはうっすら曇っていて……。
晩ごはんの後、館内の天文台施設へ行く。あまりよく解っていなかったのだけど、この施設全体は弘前市が保有していて、レストランやホテル業務は民間に委託しているという体裁らしい。昼間に行った太宰治記念館も弘前市の所有だし、3日後に行く浅虫水族館も文化事業推進のため、入館料を500円値下げしたということを知ったところなので、青森は文化事業に力を入れていてすごいな……と思う。奈良県には唯一、プラネタリウムが五條市にあったのだけど、もう壊れたまま5年間修理されていないままだ。
天文台を覗かせてもらったが、やはりあいにく曇っていて見えず……ただ、1Fでコンピューターを使って星の動きを解説してくれているらしい部屋があったので、そちらを覗いてみる。ちょうどシニアの団体に、黄道十二星座の解説し終わったところのようで、参加者はわたしと夏生さんだけだった。
「ではですね、星というのは月とちがって自分で光るしかありません。気づいてもらえないんで」
という感じで職員のひとの解説がつづくのだけど、これがぜんぶ津軽弁で、謎に胸にこみあげてくる感動があった……内容は、自分たちの方も十二星座かなあ、と思っていたがけっこう細かく、一等星の大小や距離、使用しているソフトが何かなども説明してくれてそれもちょっとびっくりした。
「なにか見たい星とかありますか?(津軽弁)」
と訊いてくれたので、高校生の頃、沖縄で見えなかったカノープスを……とリクエストしたら、それも解説してくれて、嬉しかった。たぶん1時間くらいは解説してくれたと思う。
解説が終わったあと「けっこう好きに喋ってしまってすみません。どこから来られたんですか(津軽弁)」と訊かれたので、奈良からで、あしたの観光はまだあんまり決めてないというと、岩木山神社を教えてくれた。
そういえば、『津軽』でも太宰は岩木山を「津軽富士」と呼んでいた。急遽決まった予定だけれど、明日が楽しみである。
10/15(火)
むつ、竜飛崎、とこれまでずっと海沿い移動していたので(恐山はあまり山という感じではなかった……)、一転して山中の宿に泊まってかなりリラックスできた。いや、海沿いももちろん良かったのだけど、どちらかというと、驚きや珍しさが勝っていたというか。
自分などよりもずっと生まれも育ちも奈良の山中の夏生さんは「山の方がやっぱり落ち着くなあ。海沿いは風が強くて、息がしにくいときがあったし」とも云っていた。
実際、太宰も『津軽』で「蟹田は風の町だね」と云っていたりするし、そして蟹田以外も海沿いは風がガンガンに強い。そのあたりで撮った自分たちの写真は、なかなかの強風オールバックになっている。
天文台の職員のおじさんおすすめの岩木山神社に行く。『津軽』の表紙の山と同じシルエットだった。奈良公園の奥の方を歩いているときに似た空気があって、すごく良かった。
きょうは、連日移動しながらいろいろ見てきたので、わりとゆっくりめに過ごす。コインランドリーでインナーを洗濯している間に、地元のイオンでお惣菜などを物色してお昼にした。
「いがメンチ」「かっちゃの煮物」というものを買う。いがメンチは青森の名物で、いかを使ったさつま揚げとフライの中間のような感じ。各スーパーで特色があって面白い。
「かっちゃの煮物」の「かっちゃ」は「おかあさん」の意だと思う。切り昆布、人参、糸こんにゃく、ホタテがあっさりめに炊かれている。青森のひとがめちゃめちゃカジュアルにホタテを料理に使うということが、だんだんわかってきた。
今回の旅行は朝・晩はホテルで食べていたけれど、昼はこうして地元のスーパーで土地のものを買って食べることが多かった。このあたりだと「ユニバース」や「よこまちストア」というチェーン店が有名らしい。
これ以外に地元のトップバリュにも入ったりしたけれど、共通するのはやはりりんごジュースの種類が豊富。10種類以上ある。南部せんべいもそれだけの棚があって、お土産とか銘菓というわけでなく、地元に根付いて食べられているのだなあ、と思った。
あとパンは「工藤パン」というメーカーが有名らしく「イギリスパン」のシリーズをいくつか買って食べたが美味しかった。関西だとフジパンの「シュガーマーガリンスナック」にやや近いけど、それよりあっさりしていて、ボリュームのある感じ。
午後は弘前の中心に移動して、藤田記念公園を見たり、アップルパイを食べたり。
その後、本日の宿のある三沢へ。そう、三沢に再び戻るルートなんですよね……でもまあ、恐山の秋詣りがまずありきで計画したからというか。
そのルートなのだけど、カーナビにサジェストされたルートがなかなかの山道なのだけど、有料道路……つまりけっこうなスピードで慣れたひとたちが走っている山道で、一昨日、ちいかわ的な叫び声をあげていた夏生さんがかんぜんに無言でハンドルをきっていた。
まあまあ山道は慣れているはずなのだけど、初見だし車幅も狭い……あと後続車がどんどん詰まってくるのでプレッシャーもあり……助手席のわたしも無言になって1時間半過ごし、それでもなんとか三沢に辿り着いた。
きょうから最終日まではこのホテルに連泊なので、移動もかなり楽になる。
ちなみに今後もう泊まれるかどうか解らないし、三沢にあるということでH野リゾートにしたのだけど、入ったとたんの広大さと先回りのサービスに圧倒されて、ふたりとも「ひええ……」となってしまった。
泊まり客も多かったので館内でのその数にもびびった、ということもある。これまでむつ、竜飛崎、弘前山中にいたので、人間自体を見る数もぜんぜん少なかったのである。
すごいな……と思った箇所はたくさんあって、おいおい少しずつ書いていけたらいいのだけれど、とりあえず通された部屋は自分たちが奈良で暮らしているマンションのリビングより広かった。
これまでのホテルも充分ひろかったのだけど、さすがにリビングの2倍くらいの広さの部屋はなかった。
そして大浴場が2階分ほどの天井高をつかったヒバ造りで、清々しい香りに満たされていた。露天風呂の景観は暗かったのでよく見えなかったので、これは朝また入りにこないとな……ということを思っていたものの、寝るまでずっと謎の緊張状態のままだった。
寝落ちする前、漠然とこの短歌が脳裏に浮かんだ。
リラックスしないなら死ね 自分たちが空からずっと見え続けてる╱瀬口真司
10/16(水)
H野リゾートの凄さに取り乱していた我々だったが、一夜明けてそれでもやや落ち着いてきた。
ちなみにヒバ材は、青森県の名産品。太宰治の生家もヒバ材で造られているし、その太宰治も『津軽』で「青森県では林檎は明治時代に種が入ってきて、普及しはじめたのは大正時代から。それより有名なのがヒバ材の林業である」というようなことを云っている。
そのヒバ材のチップがサシェになって、ロビーで配られていて、好きなだけ持っていって枕もとで香りを楽しむことができる、というサービスに、あらためて上手いなあ……と思ったりした。
ってゆーか、わりと深く考えずに太宰の『津軽』を旅のお供に選んだのだけど、このチョイスめちゃめちゃ良かったな……太宰自身が津軽で見たもの以上に、後日くわしく文献資料にあたって書かれているっぽくて、エッセイとしての面白さに加えてしっかりガイドブックの体裁にもなっている。
『津軽』は太宰の死の3年前に書かれたものなのだけど、中学生の頃の友達と旅行したり、姪っ子ちゃんとピクニックしたり、楽しそうな描写も多く、随所に見られるユーモアも自罰的なものではない。
もっとも、3年は人の気持ちを変えてしまうのに充分な時間で、しかもこれが書かれたのは昭和19年。終戦という社会的な不安が影響したこともあったのだろう。
きょうはこの旅のメインの、寺山修司記念館に行く。