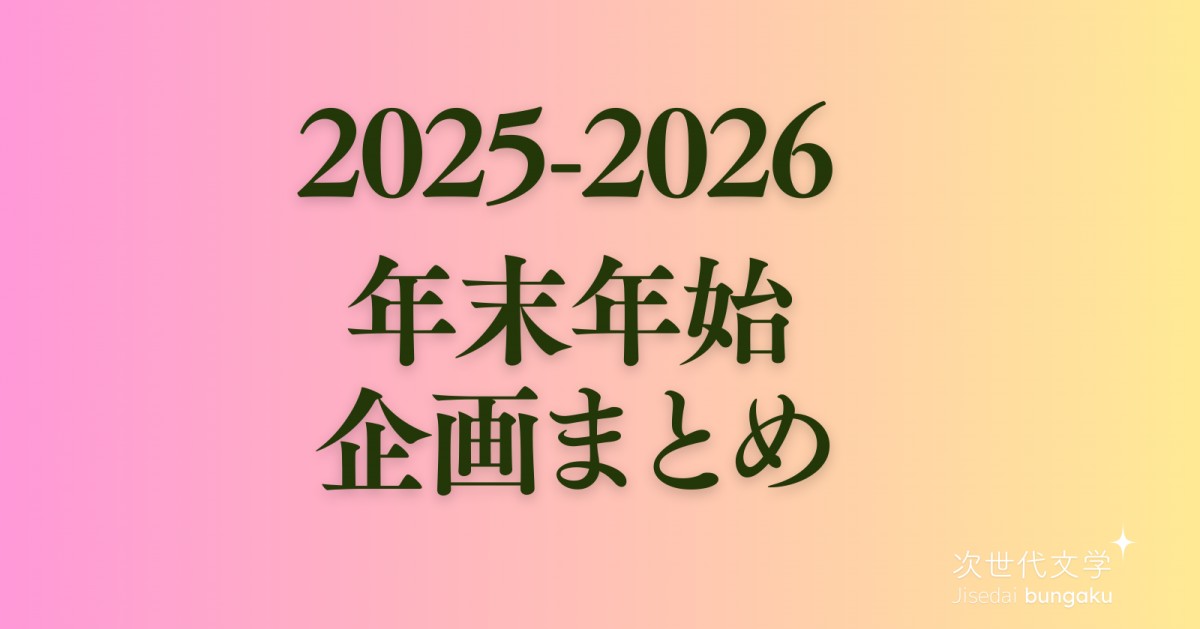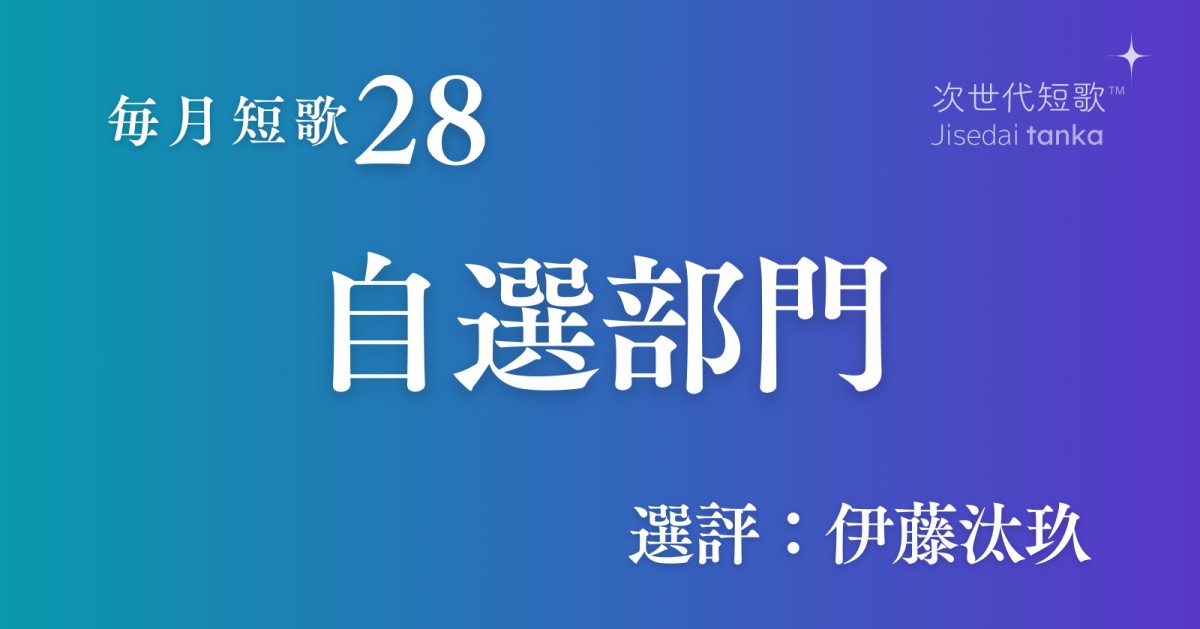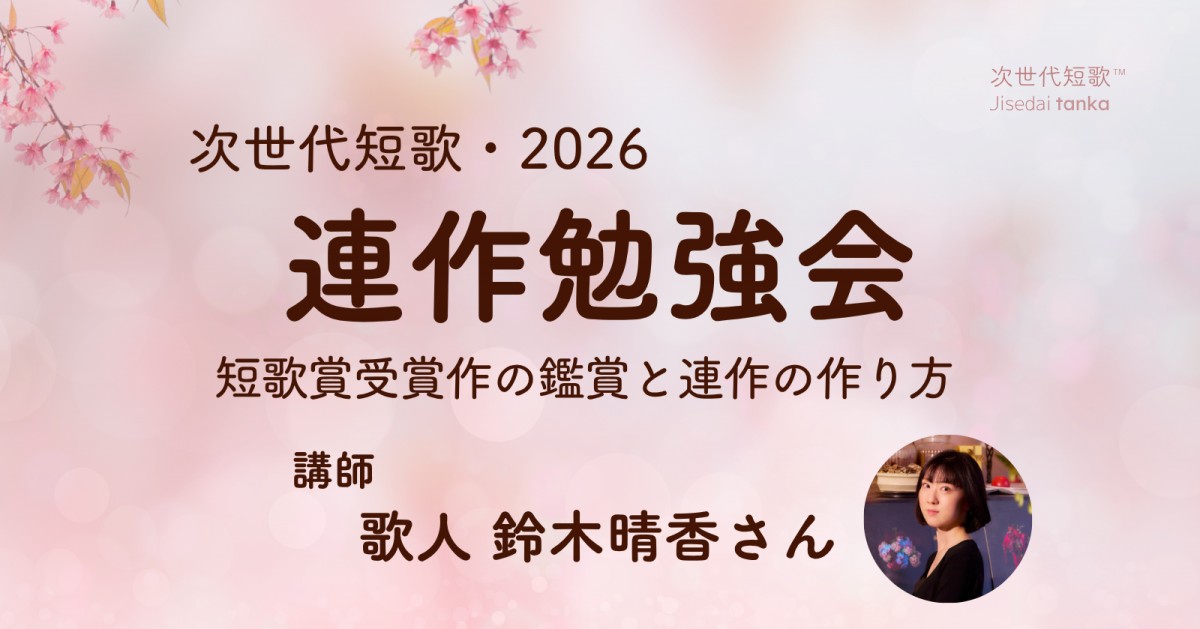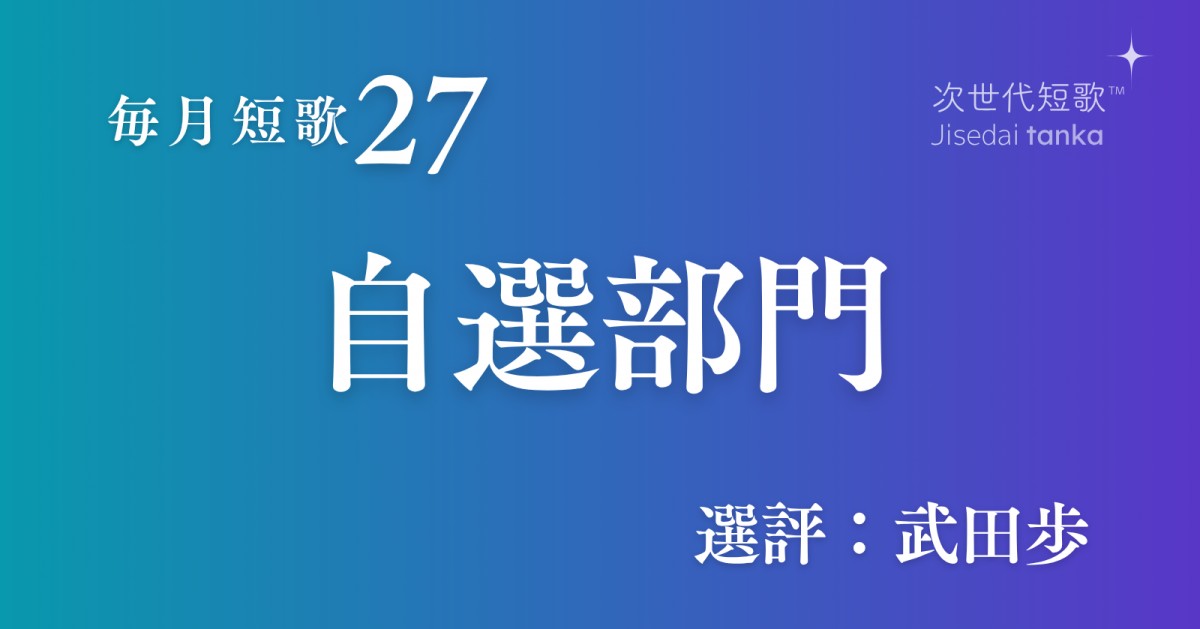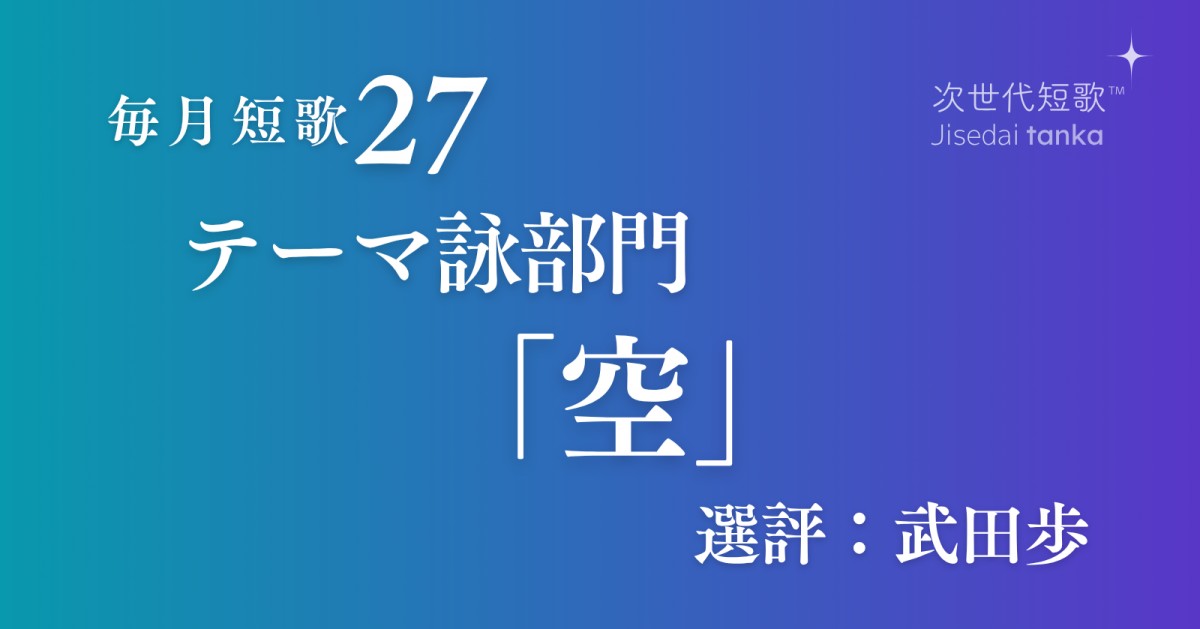第21回毎月短歌・3首連作部門(選者:スズキ皐月さん)選評発表
[次世代短歌プレミアム]
(選者の原稿を預かり、編集部で記事化させていただきました)

こんにちは! スズキ皐月です。今月も3首連作部門を担当させていただきます。
今回は春っぽい連作が多かったですね! 桜の色のように明るい連作があるかと思えば、桜が散るように憂いに満ちた連作もあり、皆さまのそれぞれの春を感じることができました。 それに強いメッセージ性のある連作も多く、 全部を紹介できないことに心苦しさを感じてしまいますね。
さて、 今回も首席、次席、三席と順番を設けてよかった作品に触れていこうと思います。
-
首席 『青空』祥
-
次席 『五月蠅』蛙黽
-
三席 『錨』よしなに
首席『青空』祥
今月の首席は祥さんの『青空』です。薄暗い雰囲気があり、それでいて幻想もあり、不思議な読み味の連作でした。
木の枝にいた頃だろうか 池にいた頃だろうか
幸福な時はいつ森青蛙
特に気になったのは上の一首です。大胆な破調の歌ではあるのですがリフレインが心地よく、 童話のような読み味を出しています。 近い韻律で同じような効果を出している歌で松平修文さんの「街へ行きしや森へ行きしや 明け方に戻り跛犬《びっこいぬ》傾きつつ水を飲む」なんかを思い出します。 このふたつの歌に通じているのは時間の奥行きでしょうか。 祥さんの歌の中では一匹の森青蛙の生きてきた場所を出して、いつ幸福だったかを問うことで時間の奥行きに蛙の生活の具体性に思考が行きます。誰もが思い浮かべるであろう蛙の無表情が少し違って見えてくるのではないでしょうか。
連作としても上手くて、 一首目でどこかにいる蛙に思いを馳せて、 二首目でその蛙の人生を、そして三首目で視線を上に向けるといった構成が自然で読んでいて臨場感を感じます。
ぜひ多くの人に読んで欲しい連作でした。
次席『五月蠅』蛙黽
次席は蛙黽さんの『五月蠅』です。一足早く夏を感じさせる連作でした。
気づいたらそうめん 5 束食っていた夕暮れ 夏の到来を忌む
最初のこの一首が連作の雰囲気の基礎のようなものをこちらに伝えてくれました。夏の人々って弱っていてみんな情けないですよね。 そうめんの食べ過ぎもあるあるで、 夏の気だるい人の様子を思い浮かべます。
誰より早く鳴き出した一匹に誰より早い八日目が来る
そして二首目で悲しさが強まります。 この歌は連作での働きを考慮しなくても、 一首でもすごくいい歌ですよね。 セミの話ではあるのですが、 どこか主体の冷ややかな視線を感じます。
この連作の主体は夏を嫌っているように見えるのですが、それでいて夏のことをよく見ているのでしょう。 このよく見ているは作者の目もそうなのでしょう。 良い短歌はするどく丁寧な観察からくるのだろうな、と思わせてくれる連作でした。
三席『錨』よしなに
三席はよしなにさんの『錨』という連作です。
「治らないから」先生は本当のことを正しく鈍器のように
片脚に錨を付けたまま生きる金魚は母を許すだろうか
死にたいと泣く子の声を聞いている静かな海の深いところで
一読で病を抱える子とその母親が見えてくる連作です。母親の強い自責の念が伝わってきます。
連作として一番魅力だなと思ったのはタイトルです。 この 『錨』 というタイトルが近すぎず、適切な距離感で三首すべてに通じています。
三首とも比喩を用いた短歌ですが、 どれも確信をしっかりつかんでいて、 それでいて嫌味のない比喩になっています。
伝えたいことが多かったり大きいときそれを短歌に組み込むのはとても難しいです。下手をすると読み手が作品の中の気持ちの強さに引いてしまうのはよくあることです。それをこの連作では比喩をうまく使うことによって大切なテーマを読み手の負担を減らしながら伝えてくれます。
おわりに
良い連作を読むと、自分もたくさん短歌を詠んでたくさん連作を作りたくなります。
ぼくが毎月短歌の選者を務めるのはこの回までの予定ですが、選者を務めているこの三か月はすごく刺激的で、 皆さんの連作を読むことで自分の創作も捗ったり、 時には悩みにドはまりしたりしました。
本当はもっとたくさんの作品に言及できたらよかったですし、語りたい作品も多かったです。そこはもうスズキの力不足ですね。
でも皆さん、 なるべく無理なく短歌続けて欲しいです。 短歌の世界は狭いので続けていればいつかどこかで皆さんと短歌の話ができる日も来るはずです。スズキはその日を待ち望んでいます。ではそれまでさようなら! またどこかで。
(選者:スズキ皐月 @hyousyoku83 )
以下、入選全作品全文のご紹介です(編集部が追記しました)